「違法アップロードするな」ではなく「合法的にアップロードしようぜ」と言おう
独断と偏見で言い切るの巻。
Happy Music Cycleキャンペーン
JASRACやレコ協、芸団協らが私的録音補償金協会からの助成を受けて行っているキャンペーン、Happy Music Cycleが個人的には癪に障る。
■ Happy Music Cycleキャンペーン公式サイト
誰がキャンペーンを行っているのか、ということを考えれば、しかたないことなのかもしれないけれど、トップページのフラッシュからしてこれ。

個人的には、エルマークのない音楽サイトJamendoから合法的に音楽をダウンロードしているので、こんなことを書かれてもクソッタレとしか言いようがない。もちろん、私のような人間は国内ではマイノリティだからなのかもしれないが、エルマークのないサイトからはダウンロードするな、と多くの人に訴えているとも読み取れて気持ちの良いものではない。
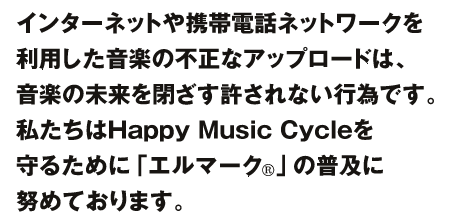
私なんかは、アーティストがCreative Commonsライセンスにて求めている表示、継承等々に従い、インターネットを利用して、Tumblrに無断でアップロードしていたりするのだが、あくまでも不正ではないので「音楽の未来を閉ざす許されない行為」ではないのだろう。安心安心。
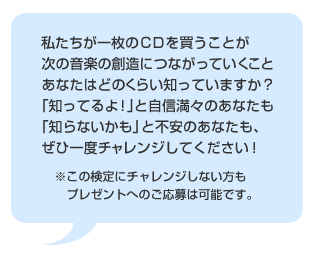 まぁ、ここまではいつものことなのでまぁいっかという感じ。ただ、その次に「けんてーごっこ」というサービスを利用したHappy Music Cycle検定というものが貼り付けられていたのだけれど、その問題が実にアレだった。その中でも特にアレなのをご紹介したい。
まぁ、ここまではいつものことなのでまぁいっかという感じ。ただ、その次に「けんてーごっこ」というサービスを利用したHappy Music Cycle検定というものが貼り付けられていたのだけれど、その問題が実にアレだった。その中でも特にアレなのをご紹介したい。
Q1:最近、ブログをやっている人も多いですが、お気に入りのCDを買った日には、それを書いている人も多いようです。次のうち、やってもいいのはどれ?
- 気に入った曲の歌詞を掲載
- 気に入った曲をアップロード
- 気に入った曲の感想を掲載
私としては気に入った曲を日々Tumblrにアップロードして公開しているので、この全てがOKだと思うのだけれど、とりあえず2.を選択。結果、不正解。正解は3.だそうで。
音楽は当然のことですが、歌詞だけであっても無断で掲載すると著作権法違反になってしまいます。ブログなどで公開する場合には、じっくり聞いた感想を掲載するところまでにしておきましょう♪
私の場合、Creative Commonsライセンスで公開されているものなので、たとえ無断でアップロードしたとしても許諾された行為であるので、違法行為にはならないんだけどね。アップロードしてもOKなものもあるし、NGなものもある、その辺の違いを書いてくれれば良いのにねぇ。
Q2:先日買ったCDがとても気に入ったので、クラスのみんなに自慢したところ、「CD−Rに焼いてきてよ♪」とみんなから頼まれました。お金をもらったら違法になると思ったので、無料で提供しましたが、後日、これは違法だということに気が付きました。では、一体、何が違法だったのでしょう?
- クラスのみんなにコピーしたことが違法
- 音楽CDをコピーすること自体が違法
- CDのことを友達に自慢したことが違法
少なくとも、私のiPodとUSBフラッシュメモリに入っているアルバムはCCライセンスで公開されているアルバムなので、気に入ったという人にはコピーしてあげているのだけれど。というより、クラスの皆がコピーしてくれと言ってきたら、ウッハウハだよなぁ*1。
で、正解は1.。
ここまで来るとおわかりいただけるかもしれないが、あくまでもHappy Music Cycleキャンペーンは音楽ビジネスで生活している人たちが、音楽ビジネスを守るために彼らに関わっているアーティストに代わって行っているキャンペーンでしかない。その最たるものが以下の設問。
Q3:音楽創造のサイクルを表した「Happy Music Cycle」。この言葉の意味として正しいのは次のどれでしょう?
- 楽曲を購入すると、めぐりめぐって音楽創造につながる
- 友達にコピーすると、めぐりめぐって楽曲が有名になる
- 音楽をブログにアップロードすると、めぐりめぐって人気者になる
この問題を見て、いぢわるな言い方をすると「結局は自分たちのビジネスに関わっているアーティスト*2からあげられる利益を守りたいだけじゃん」と思えてしまって。Creative Commonsライセンスで楽曲を公開しているアーティストたちを全力で応援する私にとっては、1.も2.も3.も全てが正解なんだから。でも、Happy Music Cycleキャンペーンの公式見解としては、1.が正解だそうで。
CCを採用するアーティストであっても楽曲を購入してもらって利益を上げることを求めてはいるけれど、自分の楽曲を友だちにコピーしたり、ブログにアップロードしてくれることも望んでいる。そうすることで、有名になり、人気者になれると信じ、願っている。さらに言えば、楽曲をフリーな形で提供しても、サポートしたいというファンはお金を出してくれる、とか、チケットを購入してライブにきて、さらにグッズを購入してくれるんだ、というアーティストもいる。
彼らにとっては、2.も3.も積極的に推奨していることであって、禁止されると困るのだ。1.だけを望んでいるのは、レコ―ディングミュージックを生業にしている人たち、そうしたビジネスに関わっている人たちであってね。だから、この設問は、そうした人たちにとって「正しいこと」を正解にしているだけで、必ずしもそれが正解であるわけではない。
この問題の解説にはこうある。
CDやダウンロード販売を通じて、音楽を購入すると、そのお金がアーティスト・作詞家・作曲家などに配分されて、次の音楽を作り出すことにつながる。そしてまた良い音楽で私たちを楽しませてくれる。それが、音楽のハッピーサイクルです。
確かに、いくら良い音楽を作っても、1円にもならないままじゃ、次の音楽を作るのは無理ですよね〜。
確かに、これはレコーディングミュージックビジネスに関わっている人々にとっては正しいのだろう。しかし、少なくとも、私の応援している人たちはレコーディングミュージックだけ守ろうとしているわけではない。彼らは自らの活動を継続していくために、自らの楽曲をコピーし、アップロードすることを推奨している。
ってことで、書き換えてみる。
コピーやアップロードを通じて、音楽の存在を伝えてあげると、アーティスト・作詞家・作曲家へのアテンションが生み出され、次の音楽を作り出すことにつながる。そしてまた良い音楽で私たちを楽しませてくれる。それが、私たちの音楽のハッピーサイクルです。
確かに、いくら良い音楽を作っても、誰にも聞いてもらえないままじゃ、次の音楽を作るのは無理ですよね〜。
コピーやアップロードを通じて、新たな音楽のサイクルに貢献することもできる場合がある、それを私は伝えたい。
ダメダメ言ってもダメ
音楽をコピーしてはいけません、アップロードしてはいけません、と言い続けても、それは真実ではないし、さらに言えば対比となるものがないためにインパクトは薄い。ならば、アップロードしてもよいものが世界には多数存在していることをアピールしてはいかがだろうか?たとえば、Creative Commonsライセンスにてパブリッシュされている楽曲は、友だちにコピーしてあげても、ウェブにアップロードしても違法ではないんだよ、と。「だから、コピー、アップロードするなら、それを望む楽曲だけにしてね!そうすれば違法アップロードにはならないよ!でも、私たちの楽曲はそうしちゃダメだからね!」といえばいい。
その上で、なぜそうしたアーティストたちが自由なコピー、アップロードを許しているのかを説明すればいい。そうすれば、自由なコンテンツと不自由なコンテンツという対比が生まれ、レコード会社からリリースされている楽曲の不自由さがより顕在化されやすくなるかもしれない。さらに言えば、不自由なコンテンツをアップロードすることが、コピー/アップロードを望む自由なコンテンツを提供してくれるアーティストに対する罪悪感を生み出すものとなるかもしれない。
揚げ足とり?本気で言ってるよ
もちろん、これまでこのダイアリーで再三述べてきたように、こうした話を一般化するつもりはない。レコード会社にとっては、自らの音楽を購入してもらうことこそが「正しい」というのは揺るぎない事実。でも、世界にはそうではない人たちもいて、そうした人たちの多くはレコード会社のようにプロモーションに割けるだけのリソースを持ち合わせていない。だからこそ、楽曲を自由に流通させることで、自らの存在をアピールしたいという思惑がある。
その思惑を潰すな、ということ、そしてその思惑は言い逃れでもなんでもなく、本気で願っている人たちがいるということ、それを知って欲しいなと。
そう、だからこそ、私は海賊コミュニティ*3を批判的に見ている。もっと自由なコンテンツを流通させろ、と。不自由なコンテンツを本当に不自由なものとしてこそ、自由なコンテンツが際だつのだから。
余談
そんなアーティストたちが取っている新たな時代の、新たな音楽ビジネス戦略がある。
そうした戦略を記述しているリソースとしては、「The Indie Band Survival Guide」や、New Music Strategiesの「20 Things」といった電子ブックがあって、これが実に面白い。前者は、非常に細かなところまで解説がなされており、本当にサバイバルのための本だと言える。日本でそのまま適用するのは難しいところもあるけれど、それでも読む価値は十二分にある。後者は、それほど細かいところまで突っ込んではいないけれど、インディペンデントなアーティストがいかにしてオンライン環境を活用し、自らの存在を広めていくか、ということに特化している。
ここしばらくの間、New Music Strategiesの「20 Things」の翻訳作業を行っていたので*4、近いうちにFC2の方で書いているブログでご紹介したいと思っている。この辺のお話はそのときにまた。乞うご期待。